今回 調べてみたのは
《やる気、モチベーション》について
目次
“ガンガンいこうぜ”と“いのちだいじに”

── モチベーションの正体と、多様な心の設計図 ──
「あいつ、やる気なくね?」
「あの人、ひとりだけ やる気満々なんですけど」
職場でも部活でも、ついそんなふうに見える相手がいる。
でも──本当にそうなのだろうか?
モチベーションは外からは見えにくい。
その「形」が人によって違うだけで、
火がついてる場所も、燃え方も、それぞれ違う。
心の健康、ハーズバーグ理論、ゆるストイック、MBTI、そして性差の視点まで含めて、いろんな角度から“モチベーション”《やる気》という曖昧で深いものを深堀してみました。
自分自身のやる気の輪郭を知ること。
そして、相手のやる気のカタチを尊重すること。
それが、これからの時代の“チーム”のあり方にも繋がってくるかもしれないので参考までに。
🔹チームで生きるということ
サラリーマンも、部活も、家庭も、気づけば誰しも「集団」「群れ」の中で生きている。
そこには必ず、役割の違いと温度差が存在する。
誰かがガンガン引っ張ってくれてこそ前に進む場面もある。
一方で、基礎を丁寧に整えてくれる存在がいなければ、組織はすぐにガタつく。
熱意で場を引っ張るタイプと、
堅実に平穏を守るタイプ。
この両者がかみ合わないと、空気は不穏になりがち。
でもそれは、どちらかが「間違っている」わけじゃない。
ただ、“モチベーションの方向”が違うだけかもしれない。
🔹モチベーション=やる気? それだけじゃない
「やる気」って聞くと、どうしても
「前向きさ」や「元気さ」みたいなイメージが先行する。
僕が前に聞いていた、若新雄純さんのVoicyでは、この様に語ってました。

「モチベーションとは、心の健康そのもの」
モチベーションを《動機づけ》と訳される。
そして動機づけは モチベーションの中の1つでしかない。
古典の考えでは、ハーズバーグ理論の
マイナスを減らす衛生要因と
プラスを増やす動機づけ要因がある。
若新さんが言うように、本当の意味でのモチベーションは、
「ガンガン行ける」時だけのことを指すのではなく、
休みたいときにちゃんと休める。
違和感があるときに立ち止まれる。
その余白があるからこそ、前に踏み出す力も自然に湧いてくる。これもモチベーションなのかもしれない。
若新雄純(わかしん ゆうじゅん)Wikipedia
プロデューサー/慶應義塾大学 特任准教授/福井県出身
・慶應義塾大学大学院での研究では、「人と組織の関係性」や「自発性のデザイン」に注力。
🔹“保守心”と“向上心”── ハーズバーグ理論から見る心の二軸
心理学者ハーズバーグが唱えた「二要因理論」では、
モチベーションを2つの要因に分けて捉える。
- 衛生要因(=保守心):
→ 不満がない状態をつくる。安全、安定、待遇、職場の環境など。 - 動機づけ要因(=向上心):
→ 満足や成長を生む。やりがい、承認、達成感など。
たとえるなら、
“いのちだいじに”は保守心。
“ガンガンいこうぜ”は向上心。
盆地徹底を守る人。
品質をコツコツ積み重ねる人。
努力が派手じゃなくても、安定を支えている人がいる。
一方で、目標を高く掲げて突き進むことで、組織に新たな風を吹かせる人もいる。
どちらが正解でも不正解でもない。
ただ、立ち位置が違うだけ。

フレデリック・ハーズバーグ(Frederick Herzberg)
アメリカ合衆国の臨床心理学者。
ケース・ウェスタン・リザーブ大学で心理学の教授、ユタ大学で経営学の教授を歴任した。
モチベーションの上昇と低下について、「動機付け要因」と「衛生要因」からなる二要因理論(英語版)を打ち出した。著書
Wikipedia
🔹「ゆるストイック」という第三の在り方

佐藤航陽さんの『ゆるストイック』には、
今の時代にぴったりの“モチベーション観”が描かれてる。
「やるべきことは明確にするけど、それを他人に押しつけない」
《意識高い系》と《意識低い系》の間にある、“淡々と続ける”という姿勢。
短期的な成果を求めすぎず、続けることそのものに意味を見出す。
この「成長教」から一歩引いた視点は、働き方や人間関係にじんわりと効いてくる。
※成長教とは、
努力しない人を悪とするような考え
- ①【衛生要因】= 保守心(マイナスを避けるための土台づくり)
- 給料・労働環境・人間関係・安全性など
- 満たされないと不満が生まれるが、満たされたからといって“やる気”には直結しない
- → 心理的安全性・ストレス管理が主なテーマ
- ②【動機づけ要因】= 向上心(プラスを求める内発的な原動力)
- 成長実感・承認・達成感・意味づけなど
- 衛生要因が整った上で「もっとやりたい」という欲が湧く
- → 目的意識・キャリア成長がテーマ
- ③【ゆるストイック】= 第三の軸(淡々と継続し、自分と折り合いをつける生き方)
- 「ガンガンいこうぜ」でも「いのちだいじに」でもない、“自分軸”で整えるスタンス
- 成果を急がず、習慣や継続自体を楽しむ
- 他人と比べず、自分のペースで深める
- 自分にも他人にも強制せず、共存を前提とした姿勢
- → 習慣性・柔軟性・自律性がテーマ
この第3の新たな軸は、
「ガンガン上を目指したいわけじゃないけど、淡々と自分のペースで働き続けたい」
「成長はしたいけど、他人からの評価には振り回されたくない」
「責任感はあるけど、過剰なプレッシャーには疲れてしまう」
みたいなニュートラルで“等身大”の働き方・モチベーションのこと。
🎯 まとめ:モチベーションの「三軸構造」
衛生要因 不満をなくす 安心、安全、整える やる気には繋がらない
動機づけ要因 成長を目指す 承認、達成、やりがい 強制や燃え尽きに注意
ゆるストイック 淡々と続ける 習慣、自己理解、柔軟 見えにくい成果/評価されにくい
この3軸で整理することで、自分や相手のモチベーションの「位置」と「向き」が見えやすくなるはず。
今の時代、多様性が重視されるからこそ、
他人のモチベーションに干渉しすぎないことが大事になってる。
🔹MBTIと素質の違い、そして“周期”という視点
僕自身、MBTIでいうと「提唱者タイプ」に属するのですが、
法則を大切にし、意味を見出しながらコツコツ積み上げていくタイプ。
なので やる気が上下するよりも、
「習慣化」や「仕組み化」で淡々と続ける方が得意。
この様に16タイプ別でも要因は変わってくる。

モチベーションを維持できない性差
最近奥さんと話していてふと気づいたことがある。
女性は身体の周期的な変化(生理など)によって、どうしても安定的に継続するのが難しいときがある。
集中したくても難しい日もある。
それを「甘え」とか「努力不足」で片づけるのは、あまりにも乱暴だと思いました。
同じように見える行動の裏にある“前提”が違えば、
モチベーションの波やエネルギーの向け方も当然違ってくる。
そのことを理解できるかどうかが、共に生きる上での分かれ道かもしれない。
🔹モチベーションは、“設計”として捉える
違いがあるのは当たり前。
でも、それを「理解できない=おかしい」と捉えてしまうと、関係性が不穏になる。
・上司と部下の温度差
・チーム内での「頑張り」の基準の違い
・誰がどこでブレーキをかけるか
・誰がいつペースを上げるか
これは「正解/不正解」ではない。
それぞれが、どういう“心の設計図”を持ってるかを知るきっかけになる。
🔹最後に
“いのちだいじに”があるから、
“ガンガンいこうぜ”が活きてくる。
どっちかに偏ると、歪みが出てしまう。
モチベーションは、火力だけではない。
ときには「燃え上がる力」であり、
ときには「冷静に保つ知恵」でもある。
お互いの違いに気づき、受け入れる。
そうすると、チーム内での心の健康も、チームの健全性も宿るのではないだろうか。
そして第3の軸の様に、相手に合わせすぎず、自分の芯を持つが、相手にそれを強要しないバランスも大事かもしれませんね。


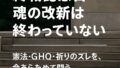
コメント