今回は
目次
ChatGPTとの対話で気づいた、AI時代に“書く”意味
—
① はじめに:AIが進化した今、「発信」って必要?
ChatGPTや他の生成AIと日々やり取りしてると、検索すら必要ない時代がくるかも…って感じませんか?
ブログやSNSの書き込みは、「バズったり、 人に見られる。」ではなくAIが引用するのに使うに変わる時代がくるのではないだろうか。
—
② 書く=自分の思考を深掘ること

AIは便利だけど、答えが簡単に出る分、自分の思考や感情が置き去りになりがち。
書くことで「なぜそう感じたのか?」を掘り下げることができる。
それが、自分の内面を整理する力になる。
自分の思考や感情をアウトプットする仕組み、装置として書く(デジタル、アナログ共に)行為は、わりと大事。
—
③ 検索されるためのブログやSNSから、“自分の記録”としての発信へ

かつてブログやSNSは、「誰かに読まれる」ことが前提だった。
検索に引っかかるようにタイトルを工夫したり、バズるような言葉選びをしたり。
どこかで“評価されるため”の発信が求められてたんだと思う。
でも今は、ちょっとずつその目的が変わりつつある。
日々の感情、疑問、経験を、“誰かのため”じゃなく“自分のため”に書く人が増えてきてる。
フォロワー数よりも、自分の思考を言語化して、記録として残しておくことに価値を感じるようになってる。
それはSNSでもブログでも一緒。
「いいね」や「RT」がなくても、自分が何を考えていたのか、何に引っかかっていたのか。
そういう思考の痕跡を、電脳空間(インターネット)に刻むような発信。
それが、もしかすると未来のAIに拾われたり、数年後の自分に読み返されたり、
まだ見ぬ誰かの“気づき”につながることがあるかもしれない。
検索されなくてもいい。バズらなくてもいい。見られなくてもいい。
けど「残す価値」はある。
そんなふうに、発信の意味が変わってきてる気がする。
もしかしたら日記の様な日常だったり、思考プロセスや人間味の部分に価値が出てくるのかもしれない。
—
④ 動物の“数え方”は後に何が残るか。人は“名を残す”、現代人は“思考を残す”

生き物の数え方には法則がある。
人間は狩猟をして動物を食べていた。
食後 いくつ食べたか数える為に、残った物を単位にしていた。
魚=尾、鳥=羽、動物=頭、
人間=名 を残すそうです。
※食べませんけどね。
小動物は匹《疋》
まだ生きている状態。
食べない小動物たちに使われてた。
[哺乳類、金魚、熱帯魚、両生類、爬虫類、昆虫]
じゃあ現代は?
歴史に名を残すのではなく、
思考や問いのプロセスを残す時代になるかも。
AIに引用されるような文章を書く
=「電脳の中に思考の種を蒔くこと」
これは「名前」よりも深く、自分の“魂のログ”を残す行為かもしれない。
—
⑤ ChatGPTは“共著者”や“編集者”──ブログやSNSの発信でも

書く途中で詰まったとき、ChatGPTと会話すると思考が整理される。
アイデア出しや文章の流れを整える役割は、もう“共著者”や“編集者”みたいな存在。
これはブログに限らず、SNSの発信でも同じだと思う。
140文字や短文でも、ChatGPTに相談すれば「どう伝えるか」「どの切り口で書くか」が見えてくる。
結果、発信の質が上がり、記録としても残しやすくなる。
AIはただのツールではなくて、“考える相手”にもなってくる。
そのやり取りそのものが、ブログやSNSの発信内容を深める土台になるのだと思う。
—
⑥ AI時代の発信の意義──SEOからSAO(生成AI最適化)へ
これまでのブログやSNSの発信は「人に検索されるため(SEO)」見てもらう、認知してもらう為に書かれてきた。
けど、生成AIが情報の仲介者になる時代、
これからは「AIに引用されるための情報(SAO=生成AI最適化)」が求められてくるのかもしれない。
AIO:AIを使って書く話
AI Optimization
SAO:AIに拾われるように書く話
Search AI Optimization
現在 Googleが利用しているのは
SEO:検索エンジン最適化
Search Engine Optimization
—
⑦ おわりに:思考の種を、電脳世界(インターネット上)に蒔く
誰に届くかは分からない。。けど、自分の感情や経験、疑問を残しておくことで、未来の誰かの“気づき”になるかもしれない。それはAIかもしれないし、自分の子どもかもしれない。
“書く(発信)”って行為は、名を残すのではなくて、「思考していた人間」として、自分をネットの世界に残し、内在させることなんかもしれない。


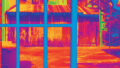
コメント